用語:process requirements
The controller, depending on the processing requirements and/or the type of system, may be programmed to control any of the processes disclosed herein, including the delivery of processing gases, temperature settings (e.g., heating and/or cooling), pressure settings, vacuum settings, power settings, radio frequency (RF) generator settings, RF matching circuit settings, frequency settings, flow rate settings, fluid delivery settings, positional and operation settings, wafer transfers into and out of a tool and other transfer tools and/or load locks connected to or interfaced with a specific system.
最近、明細書を読む際には図で整理し、内容を理解するようにしてきたのですが、抜けていたのは
「設計⇒工程管理⇒製造」という製造現場での上流からの流れでした。
問題の1文の直前には、エッチング装置の構成と、これらをcontroller(制御部)が制御することが説明されています。そしてその制御が何に基づくかが、”depending on the processing requirements and/or the type of system”です。
当初は、requirementを単に「要求」と訳していましたがその後、「要求」「要件」との違いを意識するようになりました。「こういうことができる装置がほしい」(要求)を「システム/装置としてありうる理想形」(要件)に落とし込む、という抽象⇒具体の関係で理解していました。
例えばケーキ作りでいえば、「フルーツの入った層が多いケーキが作りたい」というのが要求(ニーズ)であり、「ミルフィーユを作ろう」という要件に翻訳し、そこから温度やレシピなどの工程に落とし込む、そのように徐々に具体化するイメージです。
ただここで大切だったのは、この具体化がどの段階で起きているのか、という視点でした。「設計⇒工程管理⇒製造」という製造現場でどの段階の requirement なのかを考える必要がありました。
「設計」段階での要件は、「工程管理」段階では達成すべき要求となり、「製造」段階ではその要求を実現するための具体的な運転条件(温度、圧力、ガス流量など)として具体化されます。
つまり、(顧客)要求>要件>条件という理解(右に行くほど具体的)は、伝えられる情報の抽象度の階層化だけでなく、「設計⇒工程管理⇒製造」という移行にy9あああああああああああああ関わることで何が要求になって要件になるかは異なることになります。
要求(こうしたい)に対して、要件(こうすればできる)という設計上の方法、そして条件は実行のためのパラメータです。設計で考えれば、顧客要求に対する要件が、工程管理段階ではこれ自体が要求になる、という構造だと分かりやすいかもしれません。
controller(制御部) は、エッチング装置を構成する、処理モジュール(処理チャンバ)、搬送モジュール(VTM、ロードロック)、電源ユニット(RF発生器等)を制御するという目的のために構成され得る層です。これらのかくもじは、それぞれの処理対象や制御目的に応じて個別に制御され、controller はその際に参照するパラメータとして “processing requirements” を用います。
その制御を実行するために参照するのが”processing requirements”であることを考えると、ここでの”processing requirements”は、個々の制御に必要なパラメータとして参照される処理条件であると考えるのが自然なのだと思います。
用語:process operations
“process operations”も同様に見直します。
A suitable apparatus includes hardware for accomplishing the process operations and a system controller having instructions for controlling process operations in accordance with the present embodiments.
この文では 、apparatus(装置)がhardware と controller の2つの要素で構成されていること、そして、hardwareは処理チャンバや搬送系、電源系等の物理的な構成要素であり、これらが“process operations”を実行し、controllerは“process operations”を制御します。
どちらも、“process operations”を対象としていることから、ここでのoperationは、人による操作や装置の動作ではなく、装置が担う工程を対象としていると考え「処理工程」と読むのだったと考えます。
もしもこのoperationを動作や操作と解釈すると、制御部は個別の動作そのものを制御することになりますが、実際にはそうした動作を併せて一つの工程を実行する制御と考える方が文脈にも合うと考えます。
当初は、主語に着目して「工程」か「操作/作業」かを判断する視点が明確ではありませんでした。また、processを極力プロセスと決め打ちしすぎていたため、文中の階層を柔軟に捉える余地を狭めていたように思います。
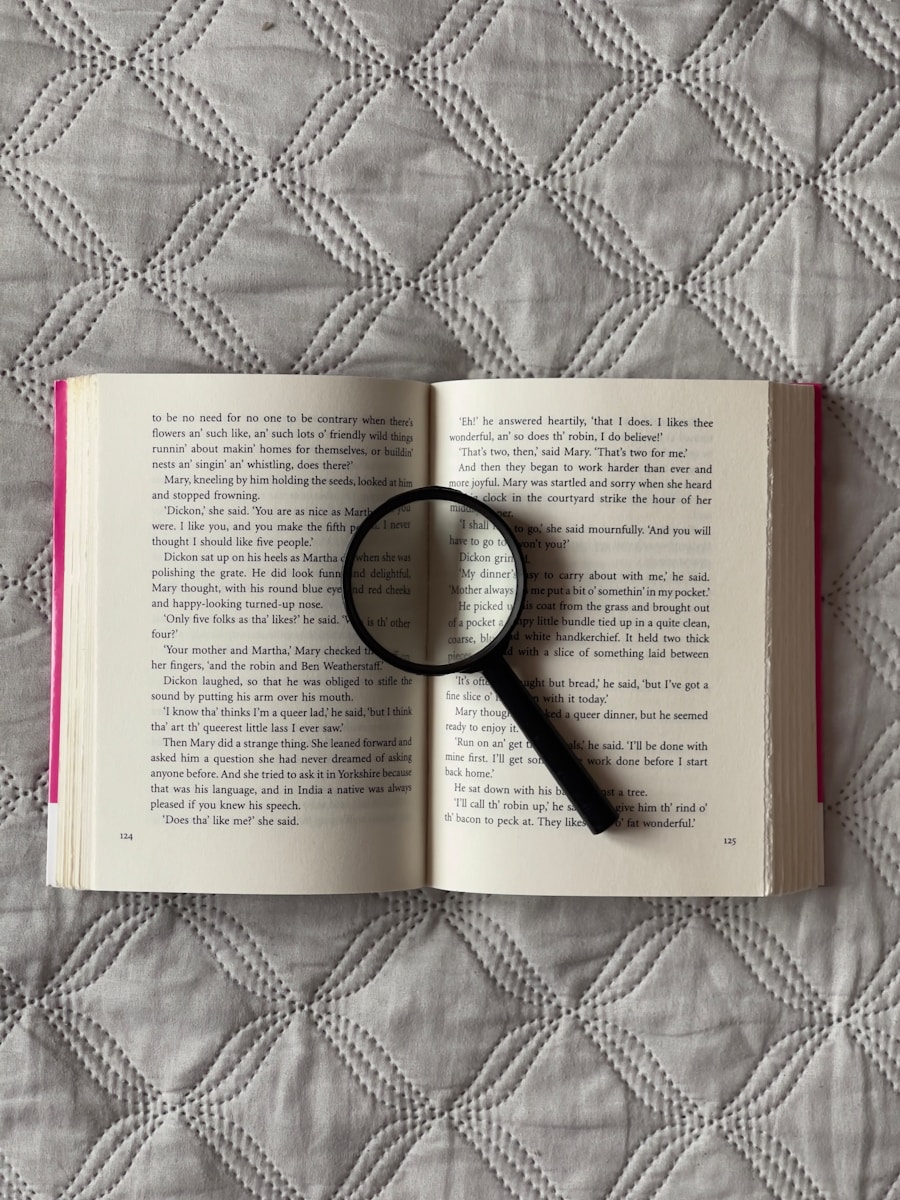


コメント