前回は次に特許の話を書くつもりでしたが、
その前にひとつ、翻訳とは一見関係ないようでいて
実は日々の会話も「言葉の扱い」そのものだなと感じた話です。
感情に支配された瞬間
子育ての中で、ふと自分の言葉の使い方に「つい言い過ぎたな」と反省する場面があります。
同じように感じる方もいらっしゃるかもしれません。
詳細は省きますが、子どもへの指摘が、売り言葉に買い言葉のような応酬になり、大いに反省する結果になりました。
冷静になって考えてみると、その言葉は子どもの行動に対する建設的な提案ではなく、
自分の中にあった焦りや未整理の気持ちが、そのまま出力された、感情をぶつけただけの言葉だったのだと思います。
言葉の向こうの本当の意味
相手がその言葉を発した背景や気持ちを少しでも理解しようとしていたら、そもそも違う言葉が出ていたはずです。
子どもの言葉も行動も、表面だけを見ていては
本当の意味がつかめないことがよくあります。
本人なりの本音や不安、うまく言葉にできない思いが、ときに攻撃的な言葉として表れることがあります。
だからこそ、言葉を額面取りに受け取って反応するのでなく
今何を伝えようとしているのか、どんな状況にあるのか、を考えながら聴く必要がある。
そのうえで「どう返したら前向きに動けるか」を考えて伝える言葉を選ぶ。
時には、言わないという選択肢も必要かもしれません。
もし今回これができてきれば、まったく違う対話になっていただろうと思います。
もちろん、いつもいつもそんなことを冷静に考えているわけではありません。
ただ、そういうふうに返すべきときが、確かにあると感じています。
対訳作業との共通点?
この相手の気持ちを想像してどう返すか考えるプロセスは、対訳中に意識している作業と、どこか通じるところがある気がします。もちろん特許の翻訳と感情のやりとりでは、前提も目的も大きく異なりますが。
翻訳ではまず、原文の文字面だけでなく文脈や背景を読む。
今回の話でいえば、子どもの言動の背後にある気持ちや状況を読み取ることと似ています。
翻訳では、意味は似ていても、その文脈での最適な用語を意識的に選ぶ必要があります。
対話でも、相手の状態やどんな結果を望んで言葉をかけるか、考えたうえで伝える言葉を選ぶべきでした。
反応から応答へ
相手の言葉そのものや自分の感情に引きずられるのではなく、
一呼吸置いて、何をどう伝えるかを選ぶこと。
それだけで、言葉の質が変わるのだと実感しています。
今回のやりとりも、いま振り返れば、子どものためではなく、
自分の気持ちが未整理なまま出てしまった言葉でした。
おわりに
特許の翻訳と感情のやりとりでは、扱う内容も目的も異なります。
ですが、言葉をどう扱うかという根本的なところで同じ構造は、思った以上に重なっていました。
日常でも翻訳でも、大切なのは反射的に反応するのではなく、意図をもって応答であること。
言葉をその置かれた背景のなかにある状態を反映するように、文脈の中で伝える言葉をすることが大切だと実感しています。地道に言葉に向き合っていきます。
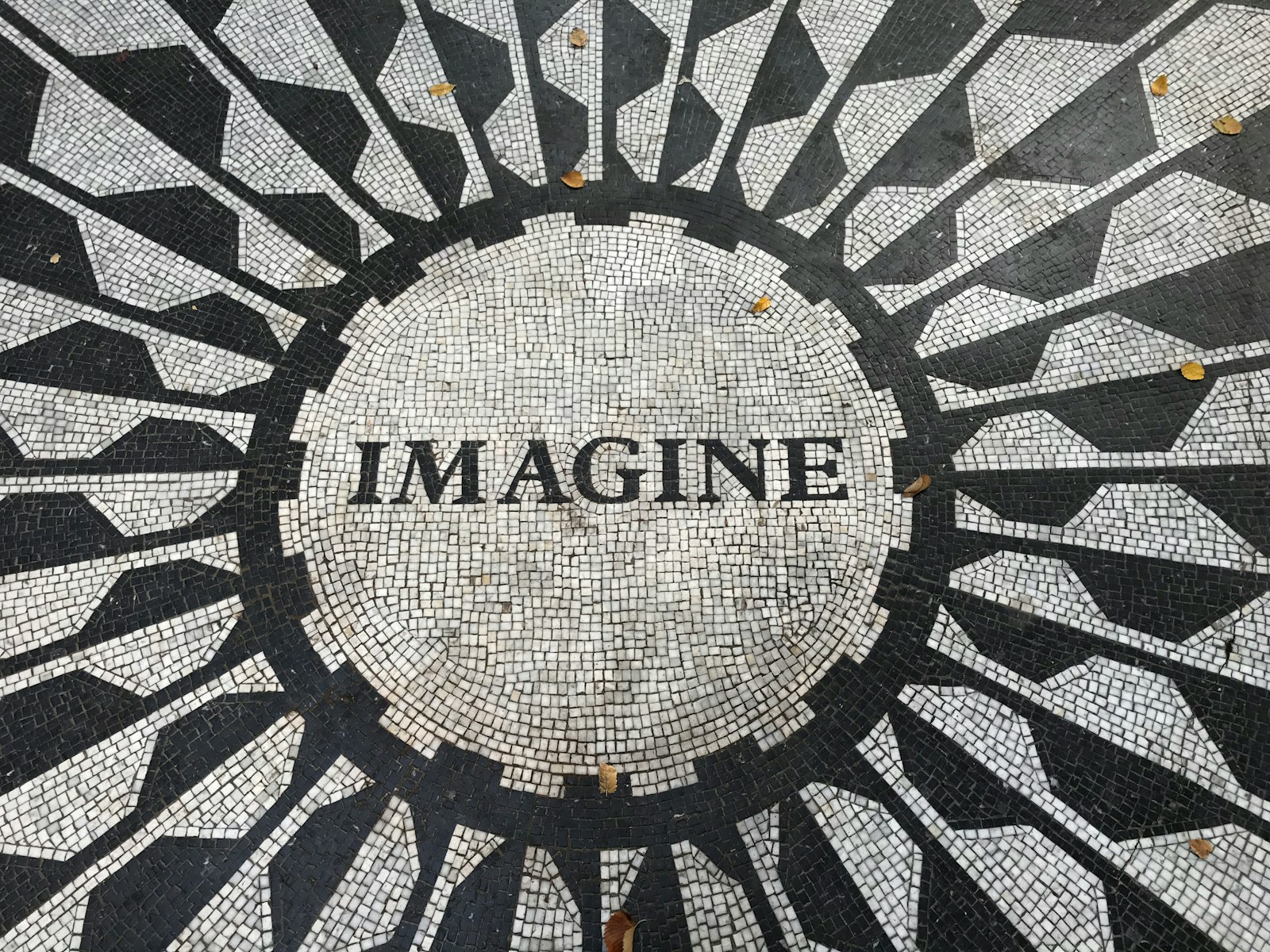

コメント